反語と疑問の理解、見分け方 | 古文完全攻略勉強法
古文の読解でつまずきやすいポイントのひとつが「反語」と「疑問」の識別です。
どちらも「か」「や」などの助詞で表されますが、意味の取り違えは主語や文脈の誤読につながります。
この記事では、高校古文・大学入試・共通テスト対策に役立つ「反語と疑問の見分け方」を具体例とともに解説します。
目次
反語と疑問の理解、見分け方
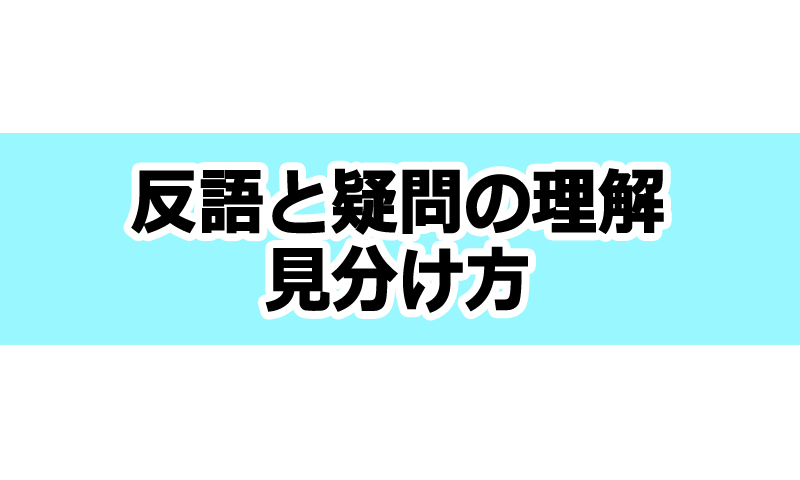
古文を読むとき、動詞や助動詞のほかにも注意すべきポイントがあります。それが、今回ご紹介する「反語」です。
はんご、と読みます。
反語とはいったい何なのか、何に気をつければいいのか、いっしょに見ていきましょう。
反語とは何か
古今和歌集の序、つまり巻頭の部分には「生きとし生けるもの、いづれか歌を詠まざりける」という一節があります。
だれが歌を詠まなかったであろう(いや、歌を詠まなかったなどということはない、だれもが歌を詠んできたのだ)という意味ですが、この「疑問」に見せかけて実際はより強い疑問、むしろ「そんなはずはない」と否定するような表現方法を「反語」とよびます。
現代でも、強い調子で疑問文を読むと「いや、そんなわけないよね!」と逆の意味で伝わりますよね。
反語には、疑問が強まりすぎて結果的に逆の意味で機能する効果があります。
反語と疑問の見分け方
古文で疑問、または反語を表すのは「か」「や」という助詞です。
よりニュアンスを強めたい場合は「かは」「やは」となることもあります。
「か」と「や」の使い分けについては、平安時代までは決まったルールがあったようですが、中世以後それが乱れたという説もあります。
古文を読解するにあたっては、どちらも同じように疑問、反語として扱ってよいでしょう。
さて、上記の古今和歌集の例もそうですが、口語と違って「か」がつくのは文末とは限りません。
口語では「~なのか?」「~ですか?」と最後に「か」をつけますが、古文では疑問を感じる部分の直後に「か」がつきます。
つまり、誰がいるかと聞きたい場合は「誰かある」となります。
ただ、ややこしいのは反語も疑問と同様の使われ方をするということです。
文をぱっと見ただけでは、疑問か反語か判断できないでしょう。
文脈から推測して、これは疑問だろう、あるいはより強い疑問で反語として解釈していいだろう、と考える必要が出てきます。
もちろん、初めからすべて正確に見分けようとするのは無謀です。
まずは助動詞を見つけ、接続を手がかりに動詞や形容詞を取り出していって、意味をとらえるところから始めてください。
動詞・助動詞の活用パターンと接続は常に最重要ですから、いつでも気をつけて見つけてくださいね。
さて、文の意味がおぼろげに見えてくると、文章の流れも何となく掴めるようになってきます。
その文章の流れにそって、この文は「疑問」で訳すのが自然なのか、それとも「反語」としてしまったほうがしっくりくるのか、考えていきましょう。
反語がわかるようになると、古文読解はだいぶ上達しているといえます。
古文は文法さえ理解できていれば、難しい単語はたいてい脚注で意味が示されているので内容理解そのものは易しいのが特徴です。
あと一息ですから、ぜひ古文を得意科目として好きになってみてくださいね。
ミニドリル(練習問題)
- 「誰か知る」—— 反語?疑問?
解答を見る
反語(誰が知っていようか、いや誰も知らない)
- 「いづれの御時にか」—— 反語?疑問?
解答を見る
疑問(どの帝の御代であったか)
- 「人やある」—— 反語?疑問?
解答を見る
疑問(誰かいませんか?)
- 「いづくにか泊つらむ」—— 反語?疑問?
解答を見る
疑問(どこに泊まっているのだろうか)
暗記のコツ・学習計画
- 「か」「や」「かは」「やは」が出てきたら下線を引き、文脈から反語か疑問かを必ず確認する。
- 古典和歌(百人一首など)の反語表現を音読して慣れる。
- 週1回は短文を集中的に練習し、必ず声に出して意味を確認する。
関連記事リンク
よくある質問(FAQ)
- Q. 疑問と反語はどう見分ければいいですか?
- A. 文脈を手がかりに判断します。「か」「や」などが文末にある場合は疑問、それ以外や否定的ニュアンスが強い場合は反語と考えましょう。
- Q. 「か」「や」の違いは覚える必要がありますか?
- A. 平安時代までは区別がありましたが、中世以降は混在しています。共通テストや入試レベルでは同じ働きをするものとして理解すれば大丈夫です。
- Q. 練習方法は?
- A. 過去問や古文読解問題で「か」「や」の用例を探し、疑問と反語を訳し分ける練習を繰り返すと定着します。


